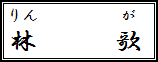 |
現行曲 | 訓法 利牟加゚ ゚ 〜りんが〜 | |
| 別字 臨河。林賀。 | |||
| 舞楽 ○ | 別名 甲子曲。 | ||

嵯峨天皇(在位809〜823)の頃に高麗の笛師下春が作るといいます。また、兵庫允の玉手公頼が作るともいいます。
子祭(11月の子の日)と甲子の日に奏するといいます。
![]()
渡物
舞楽 右方舞。平舞。舞人4人。番舞≪甘州≫。
装束 別装束
| 当曲 | 唐楽壱越調。唐楽平調。唐楽雙調。黄鐘調。盤渉調。上無調。 |
舞楽 右方舞。平舞。舞人4人。番舞≪甘州≫。
| 出時 | こ ま こ らんじょう ・高麗小亂聲 |
||
| こ ま らんじょう ・高麗亂聲 |
吹止句により終わる。 |
舞人は登台して出手を舞い、 正面立に立ち定まります。 | |
| 当曲舞 | ・高麗平調音取 | ||
| ・当曲 | 新楽。 小曲。四拍子。拍子十四。 加拍子は三度拍子。 催馬楽の律歌≪老鼠≫に合うといいます。 |
諸去肘、左百突より加拍子になり、左巻指、正面向と続きます。 | |
| 入時 | ・連吹 [当曲] | 吹止句により終わる。 | 舞人は順次退出します。 |
装束 別装束
| ほう 袍 |
朽葉顕紋紗に四手雲の地紋。金・銀・白の鼠の刺繍。袖先と裾は五七桐・唐草の金襴縁。 |
| はかま 袴 |
両練紋固地綾織に霰・四手雲の地紋。裏は紅平絹。裾に紐のない切袴。 |
| あかのおおくち 赤大口 |
紅平絹。 |
| し かい 絲鞋 |
白絹糸。底に羊の柔革。中底に畳表。絹紐で締める。 |
| べつかぶと 別甲 |
和紙製。胡粉絵具塗。四菱・七宝・亀甲の模様。青の組紐で顎に結ぶ。 |