かん げん
管絃
管絃
舞の伴奏としてではなく、楽そのものを楽しむ演奏形態をいいます。
平安期に貴族たちの間で盛んになり、我が国で独自に完成された形態です。
当時は「管絃遊び」と称し自ら楽器を奏で、演奏を楽しむことが貴族の嗜みとなっていたようで、「徒然草」や「枕草子」などにも記述が見られます。
人ごとに、我が身にうとき事をのみぞ好める。・・・<中略>・・・管絃を嗜み合へり。〜「徒然草」第八十段より〜
使用される楽器は「三管三鼓両絃」といわれ次のように分類されます。
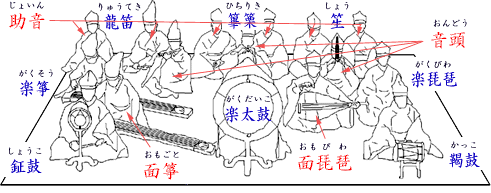
- 三管 吹物
- 笙・篳篥・龍笛
- 三鼓 打物
- 鉦鼓・鞨鼓・楽太鼓
- 両絃 弾物
- 楽箏・楽琵琶
各楽器の編成としては管が各3人、鼓が各1人、絃が各2人の総16人が一般的で、
三管について主奏者を「音頭」と呼び、それ以外の者を「助音」と呼びます。
また、楽箏と楽琵琶の主奏者をそれぞれ「面箏」「面琵琶」と呼びます。
舞を伴わないため緩やかに奏され「管絃吹」と言われます。
楽は古くは高麗楽も用いられていたようですが、現在では唐楽のみ用いられ高麗楽は用いられません。