楽器
雅楽に用いられる楽器は次の3つに分類されます。
笙
![]()
鳳凰が羽を休めた形に似ているため鳳笙とも呼ばれます。
匏と呼ばれる吹口の上に17本の竹製の管が差されていて内15本に「佐波里」と呼ばれる金属製の簧(リード)が付いています。残りの2本にも本来 簧が付いていましたが、その音を含めた和音が日本人の好みに合わなかった為か、現在では取り外され用いられていません。
見た目の竹の長さと音の高さには関係がなく、内側の見えない部分に開けられた穴までの長さによって決められています。竹管の根元に開けられた音孔をふさぐことにより、その管のみ音が出るようになっていて、息を吸っても吐いても同じ音が出ます。
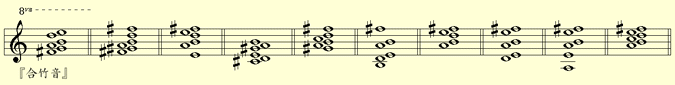
1つの音のみを出す「一竹」という奏法もあります。
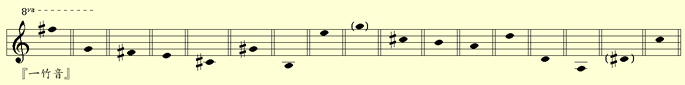
西洋楽器のハーモニカやアコーディオンといったところで和声部を受け持ち、その厳かな音は天界の響きにたとえられます。
篳篥
![]()
竹製で長さは18cmほどで表に7つ裏に2つの指孔があります。
「蘆舌」と呼ばれる葦の茎で作られた6cmほどの舌(ダブルリード)を上部に差して音を出します。
音域は1オクターブ強と狭く、音と音を滑らかにつなげる(ポルタメント)「塩梅」という奏法が特徴的です。
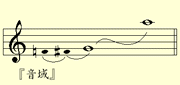
西洋楽器のオーボエといったところで主旋律を受け持ち、その力強い大きな音は人の声にたとえられます。
龍笛
![]()
竹製で長さは36cmほどで7つの指孔があります。
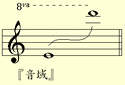
いわゆる全世界に見られる横笛の類で主旋律を装飾し、その音色は龍の鳴き声にたとえられます。
高麗笛
![]()
竹製で長さは33cmほどで6つの指孔があります。
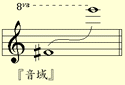
龍笛より3cmほど短く同じ運指でも「長2度」高く響きます。主旋律を装飾します。
鉦鼓
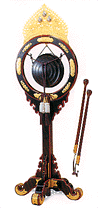
木製の台に直径15cmほどの鉦を吊るして2本の桴で内側を摺るように打ちます。各小節の拍を定めます。
片方の桴のみで単音を打つ「金」と、両方の桴で連続して打つ「金金」と呼ばれる奏法があります。
鞨鼓
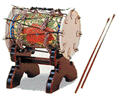
長さ30cmほどの胴の両端に直径23cmほどの皮を当て、調緒と呼ばれる紐で締めてあります。
台にのせて平らに置き左右の桴で打ちます。リズムを細かく砕いて全体を先導します。
片手で連続して打つ「片来」、両手で連続して打つ「諸来」と呼ばれる新楽奏法と、
右の桴のみで単音を打つ「壱鼓打」と呼ばれる古楽奏法があります。
三ノ鼓
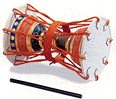
長さ45cmほどの中央がくびれた胴の両端に直径42cmほどの皮を当て、
調緒と呼ばれる紐で締めてあります。左手で抱えて持ち右手の桴で打ちます。
1つ打つ「帝」と、2つ打つ「帝帝」と呼ばれる奏法があります。
楽太鼓
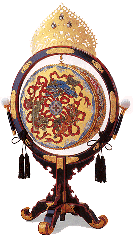
木製の台に直径50cmほどの太鼓を吊るして打ちます。大体の拍子数を定めます。
左手で弱く打つ「図」と、右手で強く打つ「百」と呼ばれる奏法があります。
楽箏
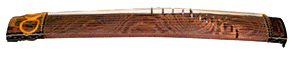
長さ180cmほどの桐製の箱に13本の絃が張られています。
右手の親指・人さし指・中指にはめた竹製の爪で絃を弾いて音を出します。リズムを細かく砕いて旋律にのせます。
4つの音で構成される「閑掻」と、3つの音で構成される「早掻」と呼ばれる奏法があります。
楽琵琶
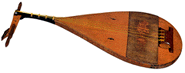
4本の絃と4つの柱を持ち、座った両膝の上に水平に構えて左手で柱を押さえ右手の撥で絃を上から下へと弾きおろして音を出します。1音から最大4音までの和音を分散し奏します。
また、右手で音を発した後に左手で柱を押さえたり放したりして音程を上げ下げする奏法があります。