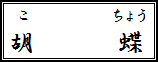 |
現行曲 | 本邦楽 | 訓法 古傳宇~こちょう~ |
| 別字 | |||
| 舞楽 ○ | 別名 胡蝶楽。蝶。花持舞。 | ||
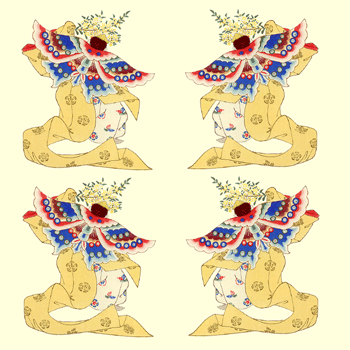
延喜6年(906)8月、宇多上皇が童相撲を御覧の時に作るといいます。
また、童相撲に楽は藤原忠房、舞は敦実親王が作るともいいます。
![]()
舞楽
右方舞。童舞。舞人4人。番舞≪迦陵頻≫。
装束 別装束
| 出時 | こ ま こ らんじょう ・高麗小亂聲 |
||
| こ ま らんじょう ・高麗亂聲 |
吹止句により終わる。 |
舞人は登台して出手を舞い、 向立に立ち定まります。 | |
| 当曲舞 | ・小音取 | ||
| ・破 | 新楽。 小曲。四拍子。拍子六(全十二)。 |
掻合寄、左巻、右追足正面向より加拍子になり飛びながら廻ります。 | |
| ・急 | 新楽。 小曲。拍子十二。 |
||
| 入時 | ・連吹 [破] | 吹止句により終わる。 | 舞人は順次退出します。 |
装束 別装束
| ほう 袍 |
青地精好紗。 |
| はかま 袴 |
白無地綾織。 |
| あかのおおくち 赤大口 |
紅平絹。 |
| あておび 当帯 |
青地金襴に龍・卍・雲の地紋。固地綾織の白紐で締める。 |
| は ね 羽根 |
大羽根・小羽根・背・腹の4つの部分を鹿革で結ぶ。革に胡粉絵具塗。 |
| し かい 絲鞋 |
白絹糸。底に羊の柔革。中底に畳表。絹紐で締める。 |
| てんかん 天冠 |
銅製。牡丹・唐草の透彫に銀鍍金。 |
| か ざ し 挿頭花 |
|
| どうはつ 童髪 |
黒長髪のかつら。 |
| と り ばな 剪採花 |
山吹の造花。 |