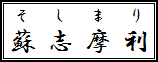 |
現行曲 | 新羅楽 | 訓法 曾志眞理〜そしまり〜 |
| 別字 | |||
| 舞楽 ○ | 別名 蘇志。蘇志摩。蘇志茂利。長久楽。廻庭楽。 | ||

旱魃の時に雨請のために舞うといいます。
素戔鳴尊が雨に遭い青草で蓑笠を作り、新羅国の曾尸茂利に到ったのを模して作るといいます。
我が国への伝来は不詳です。
近衛天皇の久安年間(1145〜1150)以来、舞は絶えていたが、明治44年(1911)に芝葛鎮によって再興されました。
![]()
舞楽
右方舞。平舞。舞人4人。番舞≪蘇莫者≫。
装束 右方襲装束 (袍は着用しない)
| 出時 | こ ま らんじょう ・高麗亂聲 |
吹止句により終わる。 |
舞人は登台して出手を舞い、立ち定まります。 |
| 当曲舞 | ・高麗雙調音取 | ||
| ・当曲 | 新楽。 中曲。四拍子。拍子九。 |
途中で向い合わせに跪き笠をかぶります。立ち上がった時より加拍子になります。 | |
| 入時 | ・連吹 [当曲] | 吹止句により終わる。 | 舞人は退出します。 |
装束 右方襲装束 (袍は着用しない)
| みの 蓑 |
生絹製。萌黄色染。 |
| とうかん 唐冠 |
平纓なし。 |
| む し 牟子 |
唐冠の上につける。 |
| かさ 笠 |
檜の樹皮製。萌黄色染。紐で顎に結ぶ。 |