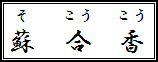 |
現行曲 | 天竺楽 | 訓法 曾加不加宇〜そこうこう〜 (常には香の字を略す) |
| 管絃 ○ | 別字 | ||
| 舞楽 ○ | 別名 蘇合。古唐蘇合香。 | ||
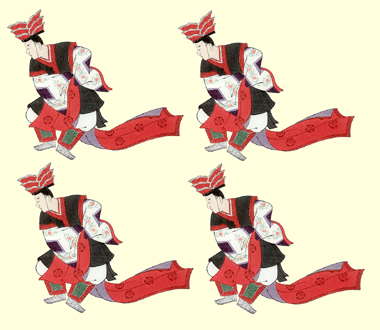
唐楽 四箇之大曲の一つで、陳の後主という人が作るといいます。 また、もとは中インドの楽で、天竺の阿育王(アショカ王 在位 紀元前272〜紀元前232)が病気になったとき蘇合草によって治癒しました。回復を祝い楽を作り、育偈という人が蘇合草を冠として舞を舞ったともいいます。
この楽には「序・破・急」および「延拍子・早拍子・只拍子」があり、打物には「八拍子・七拍子・六拍子・五拍子・四拍子・二拍子・一拍子・乱拍子・破拍子・籠拍子・約拍子・頻拍子・推拍子」があります。 また鞨鼓には全奏法である「鞨鼓八声」といわれる「阿礼声・塩短声・大掲声・王+當鐺声・沙音声・織錦声・泉郎声・小掲声」がすべて含まれています。 蘇合香の香の字は「薬を調合して一剤にする」という意味があり、このように楽体をすべて備えているのは香の字に由縁するといいます。 現行に只拍子の奏法は伝わっていませんが、秘説として序四帖・破・急にあったといいます。
我が国には桓武天皇(在位781〜806)の頃に遣唐舞生 和邇部嶋継が伝えたといいます。 その際、遊聲・序一帖の拍子八の分・序二帖・颯踏を忘却したため伝えられなかったといいます。
管絃
新楽。大曲。
舞楽 新楽。大曲。左方舞。平舞。舞人6人または4人。答舞≪新鳥蘇≫≪古鳥蘇≫≪進走禿≫。
装束 左方襲装束 諸肩袒。
| さんのじょう 三帖 |
由利吹。拍子二六。 |
| 破 | 延四拍子。拍子二十。 |
| 急 | 延四拍子。拍子二一。末四拍子加。 渡物 壱越調。平調。雙調。黄鐘調。上無調。下無調。 |
舞楽 新楽。大曲。左方舞。平舞。舞人6人または4人。答舞≪新鳥蘇≫≪古鳥蘇≫≪進走禿≫。
| 出時 | ・盤渉調調子 ・龍笛音取 |
||
| ・道行 | 遊聲が伝わらなかったため破の換頭よりを用いる。 吹止句により終わる。 |
舞人は登台して出手を舞い、 平立に立ち定まります。 | |
| 当曲舞 | じょいちのじょう ・序一帖 |
序吹。拍子二。 延楽。由利吹。拍子三。[楽拍子] 早楽。責吹。拍子七。[七拍子] 序吹。三管共に終わる。 |
|
| じょにのじょう ・序二帖 |
拍子二十。 | ||
| じょさんのじょう ・序三帖 |
延楽。拍子二六。 序吹。三管共に終わる。 |
||
| じょよんのじょう ・序四帖 |
早楽。迅責吹。拍子二六。 序吹。三管共に終わる。 |
||
| じょごのじょう ・序五帖 |
早楽。責吹。拍子二三。 序吹。三管共に終わる。 |
||
| ・破 | 延四拍子。由利吹。拍子二十。 一帖(全四帖)。 |
||
| さっ とう ・颯踏 |
|||
| ・急 [古唐急という] | 延四拍子。責吹。拍子二一。末四拍子加。三返。 三帖(全五帖)。三帖より加拍子。 |
||
| 入時 | ・重吹 [急の換頭より] |
吹止句により終わる。 | 舞人は入手を舞い退出します。 |
装束 左方襲装束 諸肩袒。
| べつかぶと 別甲 |
菖蒲甲。厚紙製。胡粉絵具塗。 |