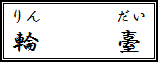 |
現行曲 | 西域楽 | 訓法 利牟太゚ ゚ 以~りんだい~ |
| 管絃 ○ | 別字 | ||
| 舞楽 ○ | 別名 | ||
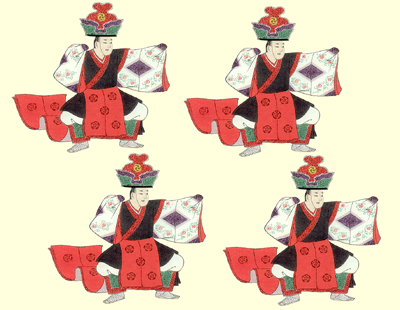
大唐の楽で德[酉+尊]という人が作るといいます。
我が国への伝来は不詳です。
もとは平調の楽であったが原曲は亡失したといいます。
延喜年間(901~923)に勅により和邇部大田麿が盤渉調に改めたといいます。
承和年間(834~848)に舞は良峯安世、詠は小野篁が作るといいます。
輪臺は中国西域にある地名で、この楽を序、
≪靑海波≫を破として連続して舞われます。
![]()
管絃
舞楽 左方舞。平舞。童舞としても。舞人4人。答舞≪敷手≫。詠あり。
装束 左方襲装束 不袒。
| 当曲 | 新楽。 中曲。早八拍子。拍子十六。末四拍子加。 渡物 平調。黄鐘調。 |
舞楽 左方舞。平舞。童舞としても。舞人4人。答舞≪敷手≫。詠あり。
| 出時 | ・盤渉調調子 ・龍笛音取 |
||
| ・延輪臺 [管絃吹] | 吹止句により終わる。 | ≪靑海波≫の二﨟をはじめとして≪輪臺≫の舞人4人を含み、終わりは≪靑海波≫の一﨟の総40人が舞台の下を一廻りしてから舞台の後ろに一列に並びます。[垣代という] 舞人は楽屋に入り≪輪臺≫は甲を、 ≪靑海波≫は袍を改めて太刀を佩きます。 舞人以外は懐より反鼻を出して手に持ちます。舞師・琵琶・笙・篳篥・龍笛の各1人が列の後ろに並びます。[垣代楽人という] 管方にも絃が加わります。[管絃舞楽という] 舞人は登台します。 | |
| 当曲舞 | ・当曲 | 新楽。 中曲。早八拍子。拍子十六。末四拍子加。 二返。一帖~二帖。 |
略式の場合、二帖までで終わります。 |
| ・詠 | |||
| ・輪臺音取 | 以降、音取と吹渡は垣代楽人によって奏されます。 | ||
| ・詠 | |||
| ・唱歌 | |||
| ・輪臺吹渡 | 早只拍子。 | ||
| ・当曲 | 一返。 三帖。 |
||
| ・詠 | |||
| ・輪臺音取 | |||
| ・詠 | |||
| ・唱歌 | |||
| ・輪臺吹渡 | |||
| ・当曲 | 一返。 四帖。吹流しで終わる。 |
一﨟・二﨟と三﨟・四﨟は位置が入れ替わり、一﨟と二﨟は降台し三﨟と四﨟は終わりまで舞います。 | |
| 入時 | ・靑海波 | 一帖。 | 三﨟と四﨟は降台します。 |
装束 左方襲装束 不袒。
| べつかぶと 別甲 |
和紙製。三色金襴張。四手雲の地紋。啄木平打紐で縁取。 三巴の金具。2枚の垂尾。裏は紅絹。 |