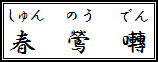 |
現行曲 | 唐楽 | 訓法 志由牟阿不傳゚ ゚ 牟〜しゅんのうでん〜 |
| 管絃 ○ | 別字 | ||
| 舞楽 ○ | 別名 天長寶壽楽。和風長壽楽。天長最壽楽。梅苑春鶯囀。天壽楽。 | ||
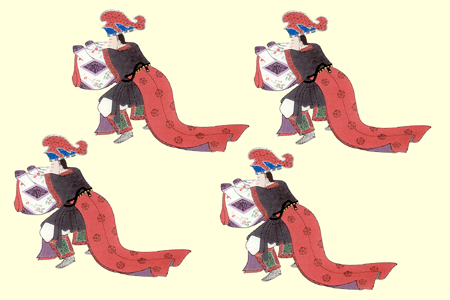
唐楽 四箇之大曲の一つで、合管青という人が作るといいます。 大国で春宮の立つ日(立太子の日)に楽官が奏したところ鶯が舞い降りてきて百回囀ったといいます。 また唐の高宗(在位650〜683)が夜明けに鶯の声を聞き、楽工の白明達に命じてこれを写させたともいいます。
我が国には文武天皇(在位697〜707)の頃に遣唐使 粟田道麿が伝えたといいます。 承和12年(845)正月8日、竜尾道で舞師 尾張浜主が115歳でこの楽を舞ったといいます。その舞が高齢を思わせず素晴らしかったため仁明天皇(在位833〜850)は天長寶壽楽と名付けたといいます。 めでたい楽として立太子の礼に度々奏されてきました。また、女性10人により舞われたという記述もあります。
昭和42年(1967)3月、国立劇場の第2回雅楽公演で宮内庁楽部によって明治以来初めて全楽一具が奏されました。
管絃
新楽。大曲。
舞楽 新楽。大曲。左方舞。平舞。女舞(10人)としても。舞人6人または4人。答舞≪新鳥蘇≫≪古鳥蘇≫≪退走禿≫。
装束 左方襲装束 諸肩袒。
| さっ とう 颯踏 |
早八拍子。拍子十六。半帖以下加。 渡物 雙調。 |
| じゅ は 入破 |
早六拍子。拍子十六。半帖以下加。 渡物 雙調。黄鐘調。盤渉調。太食調。 |
舞楽 新楽。大曲。左方舞。平舞。女舞(10人)としても。舞人6人または4人。答舞≪新鳥蘇≫≪古鳥蘇≫≪退走禿≫。
| 出時 | ・壱越調調子 ・龍笛音取 |
||
| ゆ せい ・遊聲 |
序吹物。拍子なし。 吹流しで終わる。 |
舞人は登台して出手を舞い、 平立に立ち定まります。 | |
| 当曲舞 | ・序 | 序吹物。拍子十六。 一帖(全一帖)。三管共に終わる。 |
|
| さっ とう ・颯踏 |
早八拍子。於世吹。拍子十六。 一帖(全二帖)。吹流しで終わる。 |
||
| じゅ は ・入破 |
早六拍子。於世吹。拍子十六。 一帖(全四帖)。吹流しで終わる。 |
||
| てっしょう ・鳥聲 |
序吹物。拍子十六。 一帖(全二帖)。三管共に終わる。 |
||
| きっしょう ・急聲 |
早六拍子。於世吹。拍子十六。半帖以下加。 一帖(全二帖)。鳥聲より連奏。序吹により三管共に終わる。 |
||
| 入時 | ・壱越調調子 にゅうぢょう ・龍笛入調 |
吹止句により終わる。 |
舞人は入手を舞い退出します。 |
装束 左方襲装束 諸肩袒。
| べつかぶと 別甲 |
鳳凰甲。厚紙製。金襴張。 |