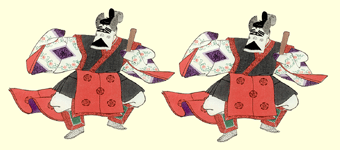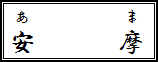 |
尰峴嬋 | 揤幈妝 | 孭朄 垻崃乣偁傑乣 |
| 娗尲 側偟 | 暿帤 埬杸丅 | ||
| 晳妝 仜 | 暿柤 堿梲抧捔嬋丅 | ||
椦梂敧妝偺堦偮丅
嵐懮挷偺妝丅
愄丄偁傞幰偑棾媨偺曮嬍傪搻傕偆偲巚偄棾彈偑岲傓悵偺柺傪偮偗偰偟偺傃崬傒丄庱旜傛偔曮嬍傪搻傒弌偡條傪晳偄偵偟偨傕偺偲偄傢傟傑偡丅
妝偼揤幈偺妝偱丄彸榓擭娫(834乣848)偵戝屗惔忋偑夵嶌偟偨偲偄偄傑偡丅
徍榓39擭(1964)俁寧俈擔丄搶嫗暥壔夛娰戝儂乕儖偱奐偐傟偨晳妝偺崙壠巜掕寍擻摿暿娪徿夛偱媨撪挕妝晹偵傛偭偰愴屻弶傔偰岞奐偝傟慡妝偑憈偝傟傑偟偨丅
晳妝
屆妝丅拞嬋丅嵍曽晳丅憱晳偵嬤偄丅摱晳偲偟偰傕丅晳恖俀恖丅摎晳佱僯晳佲佱慼棙屆佲(摱晳偺帪)丅殦帉偁傝丅
憰懇 嵍曽廝憰懇丂彅尐逯丅
| 弌帪 | 丒堧墇挷挷巕 丒棿揓壒庢 |
||
| 丂 傠偔 偝傫偒傘偆偝傫丂丂丂傠偔丂傠 丒榋嶰嬨嶰偺幁楰 |
懪暔偺傒 | 榋亅晳恖偼柺傪拝偗傞丅 嶰亅妝壆傪弌傞丅 嬨亅晳恖偼恑弌偡傞丅 嶰亅晳恖偼搊戜偡傞丅 | |
| 丂 傜傫 偠傚 丒槳彉 |
懪暔偼佱槳彉佲丅棿揓偼佱埨杸槳彉佲丅 悂巭嬪偵傛傝廔傢傞丅 |
弌庤傪晳偄傑偡丅 堦麧偼屻塃嬿偱晳偄廔傢傝幬峴偟偰惓嵍嬿偱屻柺岦偵丄擇麧偼屻塃嬿偱惓柺岦偵棫偪掕傑傝傑偡丅 | |
| 摉嬋晳 | 槳氵傪晳偄傑偡丅 堦麧偼惓嵍嬿丄擇麧偼屻塃嬿偱岦偐偄崌偭偰晳偄廔傢傝傑偡丅 | ||
| 偝偊偢傝 丒殦 |
巒傔偼柍妝丅搑拞傛傝懪暔偼佱槳彉佲丅棿揓偼佱埨杸槳彉佲丅 悂巭嬪偵傛傝廔傢傞丅 |
殦帉偼崱偼彞偊傑偣傫丅 | |
| 丂 偟傖偔偝偟丂偰 丒鈹巜庤 |
懪暔偼佱槳彉佲丅棿揓偼佱埨杸槳彉佲丅 | 鈹傪怳傝側偑傜幬傔偵峴偒堘偄丄晳嵗偑曄傢偭偨偲偙傠偱鈹傪崢偵憓偟傑偡丅晳恖偼杮嵗偵栠傝傑偡丅 | |
| 丂 偆偪偺傏傞偰 丒懪搊庤 |
悂巭嬪偵傛傝廔傢傞丅 |
惓柺岦偵側傞晳庤傪宱偰丄惓嵍嬿偲屻塃嬿偵岦偐偄崌偭偰晳偄廔傢傝丄崢偺鈹傪幏傝傑偡丅 | |
| 擖帪 | 丒槳彉 | 懪暔偼佱槳彉佲丅棿揓偼佱埨杸槳氵佲丅 悂巭嬪偵傛傝廔傢傞丅 |
晳恖偼擖庤傪晳偄傑偡丅 擇麧偑崀戜偟偨屻傕堦麧偼偟偽傜偔晳偄懕偗丄崀戜偟傑偡丅 |
憰懇 嵍曽廝憰懇丂彅尐逯丅
| 偐傫傓傝 姤 |
柍栦姤丅幗幯丅 |
| 偗傫偊偄 姫銞 |
暯銞傪姫偒崟攼嫴偱偼偝傓丅 |
| 丂偍偄偐偗 巺+埾(巺傊傫偵埾) |
崟攏栄偱敿寧宍丅 |
| 偧偆傔傫 嶨柺 |
巻偵敄對挘丅俀杮偺昍偱姤偵偮偗傞丅拪徾壔偝傟偨恖偺婄丅(摱晳偺帪偼梡偄側偄) |
| 偟傖偔 鈹 |
塃庤偵帩偮丅 |