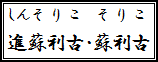 |
現行曲 | 訓法 志牟曾利古〜しんそりこ〜 曾利古〜そりこ〜 | |
| 別字 進曾利古。曾利古。 | |||
| 舞楽 ○ | 別名 竈祭舞。 | ||
由来については不詳です。
応神天皇(在位270〜310)の頃、酒造百済人の須須許理が来朝し酒を献ずる。古くは酒を造るとき竈と井戸を祭る風習があり、これに由来するともいいます。
楽と調子を秘曲とするため原曲は絶えたといい、
≪埴破≫≪狛桙≫を用います。
![]()
舞楽
右方舞。平舞。童舞としても。舞人4人。番舞≪菩薩≫≪壹鼓≫≪安摩≫(童舞の時)。
装束
進蘇利古
| 出時 | い ちょう し ・意調子 |
||
| ・当曲 | ≪埴破≫ 吹止句により終わる。 |
舞人は登台して向立に立ち定まります。 | |
| 当曲舞 | 左巻指正面向より加拍子になり正面向に舞い終わります。 | ||
| 入時 | (奏楽なし) | 舞人は退出します。 |
蘇利古
| 出時 | い ちょう し ・意調子 |
||
| ・当曲 | ≪狛桙≫の返付より 吹止句により終わる。 |
舞人は登台して向立に立ち定まります。 | |
| 当曲舞 | 左巻指正面向より加拍子になり正面向に舞い終わります。 | ||
| 入時 | (奏楽なし) | 舞人は退出します。 |
進蘇利古 右方襲装束 片肩袒。
| かんむり 冠 |
無紋冠。漆紗。 |
| けんえい 巻纓 |
平纓を巻き黒柏挟ではさむ。 |
| おいかけ 糸+委(糸へんに委) |
黒馬毛で半月形。 |
| ぞうめん 雑面 |
紙に薄絹張。2本の紐で冠につける。抽象化された人の顔。 |
| ず ばい 白楚 |
木製。胡粉絵具塗。先端に白毛。 曾利古ともいう。後参桴より小さい。(古くは白木の棒のようなものであったという) |
蘇利古 右方襲装束 諸肩袒。
| かんむり 冠 |
無紋冠。漆紗。 |
| か ざ し 挿頭花 |
|
| けんえい 巻纓 |
平纓を巻き黒柏挟ではさむ。 |
| おいかけ 糸+委(糸へんに委) |
黒馬毛で半月形。 |
| ぞうめん 雑面 |
紙に薄絹張。2本の紐で冠につける。抽象化された人の顔。(童舞の時は用いない) |
| しゃく 笏 |
|
| ず ばい 白楚 |
木製。胡粉絵具塗。先端に白毛。 曾利古ともいう。後参桴より小さい。(古くは白木の棒のようなものであったという) |
