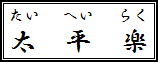 |
現行曲 | 唐楽 | 訓法 太以辺以羅具~たいへいらく~ |
| 管絃 ○ | 別字 泰平楽。 | ||
| 舞楽 ○ | 別名 武昌太平楽。武将破陣楽。項荘鴻門曲。五方師子舞。城舞。巾舞。 | ||
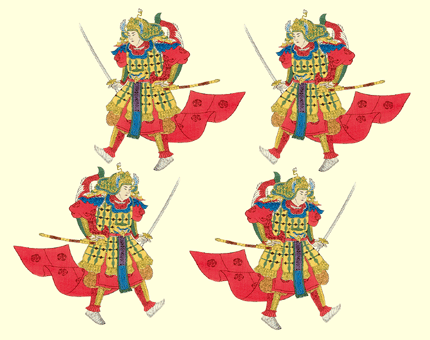
五破陣楽の一つ。
漢の高祖と楚の項羽が鴻門で宴を催した時に、項羽の臣の項荘が剣を抜いて舞いながら高祖を殺害しようとした。項羽の叔父の項伯もまた剣を抜き舞いながら高祖を守ったため殺害できなかった。この剣舞を模したといいます。
我が国へは文武天皇(在位697~706)の頃、伝えられたといいます。
めでたい楽とされ、明治天皇の即位の大礼(1867)以来、大饗の第2日目に≪萬歳楽≫とともに舞われることになりました。 現在でもよく舞われ左方武舞の代表的なものです。
![]()
管絃
舞楽 左方舞。武舞。舞人4人。答舞≪狛桙≫≪陪臚≫。
装束 別装束
| ちょう こ し 朝小子 |
新楽。 中曲。延四拍子。拍子十二。末四拍子加。 唐の王子誕生の時に奏すといいます。 |
| ぶ しょう らく 武昌楽 |
新楽。 中曲。延八拍子。拍子二十。末六拍子加。 渡物 黄鐘調。 |
| がっ か えん 合歡鹽 |
新楽。 中曲。早四拍子。拍子十六。後度二十。末四拍子加。 渡物 壱越調。雙調。黄鐘調。盤渉調。下無調。 五音が調い、歓喜の聲を備えている故に合歡鹽と名付けるといいます。 |
舞楽 左方舞。武舞。舞人4人。答舞≪狛桙≫≪陪臚≫。
| 出時 | ・太食調調子 ・龍笛音取 |
||
| ・道行 ≪朝小子≫ | 新楽。 中曲。延四拍子。拍子十二。 吹止句により終わる。 |
舞人は登台して出手を舞い、鉾の石突を舞台に立て1列となります。 四﨟の出手が終わると左右に分かれ向立の後に、後面向・正面向に跪き鉾を置きます。 | |
| 当曲舞 | ・破 ≪武昌楽≫ | 新楽。 中曲。延八拍子。拍子二十。 二帖。志止禰拍子により終わる。 |
向立に立ち、途中で鉾を取り舞います。 背合わせに舞い終わり鉾を置きます。 |
| ・急 ≪合歡鹽≫ | 新楽。 中曲。早四拍子。拍子十六。 亂聲吹止句により終わる。 |
向立に立ち、途中で太刀を抜き舞います。入違いに跪き舞い終わり太刀を納めます。 | |
| 入時 | ・重吹 [急] | 急の中段より奏す。 吹止句により終わる。 |
舞人は入綾(入手を舞い順次降台しますが、降台する舞人以外は舞を続ける)を行い退出します。 |
装束 別装束
| ほう 袍 |
紅地顕紋紗。 |
| はかま 袴 |
茶色(比曽久)の綸子に蓮・唐草の地紋。白綾織の帯。 |
| あかのおおくち 赤大口 |
紅平絹。 |
| よろい 鎧 |
挂甲。革製。漆で箔押し。金と紫の平打組紐。腰に鈴。背に金環と赤の太編揚巻紐。 |
| かたくい 肩喰 |
木製。龍頭。 |
| おびくい 帯喰 |
木製。漆塗。鬼面。 |
| や な ぐ い 胡[竹+祿] |
箱は木製で胡粉絵具塗。4本の矢はU字形で上下を逆に固定されている。 |
| ぎょ たい 魚袋 |
弓を魚の形に抽象化したもの。魚吸魚。 |
| かたあて 肩当 |
紅地と縹地の金襴。啄木平打紐で縁取。 |
| すねあて 臑当 |
革製。金地唐草の透彫に金箔押し。蝶番と玉。 |
| こ て 籠手 |
紅地と縹地の金襴。彫込み革に金箔押し。中央に十文字に玉17個。 |
| きんたい 金帯 |
革製。黒漆塗。本手に桐6個・竹4個、上手に桐・竹1個の毛彫の金具。 紅組紐で締める。 |
| ひら お 平緒 |
ドシ織で白と紫の淡染。鳳凰と桐の刺繍。 |
| たれひら お 垂平緒 |
平緒と共布。五彩の房。 |
| し かい 絲鞋 |
白絹糸。底に羊の柔革。中底に畳表。絹紐で締める。 |
| かぶと 甲 |
鉢と錣は鞣皮製。黒漆塗。表は金地唐草。筋に玉。頂きに水煙。 |
| た ち 太刀 |
衛府の太刀。鞘は金梨地に桐・竹の蒔絵。金具は唐草の透彫。柄は白鮫皮。 |
| ほこ 鉾 |
木製。剣先と鍔は金箔おき。柄は黒漆塗に四菱の金蒔絵。鰭は赤地錦に四手雲・三巴の金具。蛇の飾り。(左手は剣印) |