 |
現行曲 | 林邑楽 | 訓法 古牟志゚ ゚ 由〜こんじゅ〜 |
| 管絃 ○ | 別字 | ||
| 舞楽 ○ | 別名 醉胡楽。宴飮楽。 | ||
林邑八楽の一つ。
班蠡という人が作るといいます。胡国の人が酔ってこの曲を奏すその姿を模して舞に作るといいます。 また、承和年間(834〜848)に楽は大戸清上、舞は大戸真縄が作るともいいますが再興したものと思われます。
我が国には天平8年(736)に来朝した林邑国の佛哲が伝えたといいます。
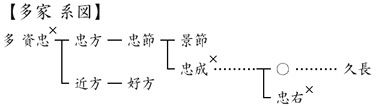
この舞は多家が伝承していましたが、康和2年(1100)に多 資忠が山村正連に殺害されて一時断絶しました。しかし、勅定をもって久我 雅実より資忠の子 忠方に伝えられました。 その後、忠節・景節・忠成と伝えられましたが、建永元年(1206)に忠成は景節の子に殺害されまた断絶しました。再び勅定によって承元元年(1207) 忠節より舞を伝授していた源 雅行が資忠の孫 好方に伝えました。 さらに嘉吉元年(1441)には忠成の子孫である忠右が殺害されまたもや断絶しました。その後 享保20年(1735)に忠成の子孫である久長に久我家より伝えられ再興されました。
管絃
舞楽 左方舞。走舞。舞人1人。答舞≪新靺鞨≫≪林歌≫。
装束 別装束
| 序 | 渡物 雙調。 |
| 破 | 古楽。 小曲。早四拍子。拍子十四。末六拍子加。 催馬楽の呂歌≪田中井戸≫に合うといいます。 渡物 平調。雙調。黄鐘調。盤渉調。太食調。上無調。 |
舞楽 左方舞。走舞。舞人1人。答舞≪新靺鞨≫≪林歌≫。
| 出時 | りん ゆうらんじょう ・林邑亂聲 |
吹止句により終わる。 |
舞人は登台して出手を舞い、 桴を左手に立ち定まります。 |
| 当曲舞 | ・音取 | ≪壱越調音取≫か≪迦陵頻音取≫ | |
| ・序 | 古楽。 小曲。序吹物。拍子七。二返。 二帖。 |
||
| ・破 | 古楽。 小曲。早四拍子。拍子十四。末六拍子加。 七帖。二帖の末二より加拍子。 |
桴は度々持ち替えられ、最後は右手に舞い終わります。 | |
| 入時 | ・重吹 [破] | 吹止句により終わる。 | 舞人は入手を舞い退出します。 |
装束 別装束
| ほう 袍 |
紅地顕紋紗に四手雲の地紋。 |
| りょうとう 裲襠 |
貫頭衣。白地唐織物。淡染の生絹の毛縁。前背面に各々2個の丸紋。 |
| はん ぴ 半臂 |
裾の脇に襴のつく続半臂。黒羽二重。裏は浅黄羽二重。 |
| わすれお 忘緒 |
半臂と共布。 |
| はかま 袴 |
白地唐織物。白綾織の帯。裾の紐を足首でくくる。 |
| あかのおおくち 赤大口 |
紅平絹。 |
| あておび 当帯 |
銅製。牡丹唐草の透彫に金鍍金。周囲に覆輪金具。裏は紅綸子。紅八打紐で締める。 |
| べつくつ 別沓 |
革製。黒漆塗。立挙は折下げ紅錦張。沓帯は黒漆塗革と金属製。 |
| めん 面 |
木製。大面。茶漆塗。頭部に茶色の毛。目と歯は銀箔おき。唇は赤漆塗。 |
| む し 牟子 |
白地金襴に桐・唐草の地紋。裏は紅綸子。3本の組紐で結ぶ。 |
| ばち 桴 |
右手に持つ。木製。黒漆塗。酒杓を模す。 |
