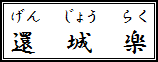 |
現行曲 | 唐楽 | 訓法 計゚ ゚ 牟志゚ ゚ 也宇羅具〜げんじょうらく〜 |
| 管絃 ○ | 別字 | ||
| 舞楽 ○ | 別名 見蛇楽。還京楽。 | ||
乞食調の楽。
唐の玄宗(在位712〜755)が兵を挙げ、韋后を誅して京師に還って≪夜半楽≫とともに作ったといいます。
宗廟で奏すると霊魂が蛇となって出現したため見蛇楽と名付けたといいます。また、西国の人は好んで蛇を食する、その蛇を求め得て喜ぶ姿を模して舞うともいいます。 また、大国で王の行幸・還御の時に大官が奏するともいいます。
我が国への伝来は不詳です。
左方舞と右方舞に用いられ、奏楽・舞手に違いがあります。
![]()
管絃
舞楽 左方舞。右方舞。走舞。童舞としても。舞人1人。
左方 ─ 答舞≪八仙≫≪納曾利≫≪拔頭(右方)≫。右方 ─ 番舞≪拔頭(左方)≫≪春庭楽≫。囀詞あり。
装束 別装束 左方・右方ともに同じ装束を用いる。
| 当曲 | 古楽。 中曲。早只八拍子。拍子十八。半帖以下加。 |
舞楽 左方舞。右方舞。走舞。童舞としても。舞人1人。
左方 ─ 答舞≪八仙≫≪納曾利≫≪拔頭(右方)≫。右方 ─ 番舞≪拔頭(左方)≫≪春庭楽≫。囀詞あり。
| 出時 | こ らんじょう ・小亂聲 |
||
| らん じょ ・亂序 |
打物は≪亂序≫。龍笛は≪陵王亂序≫の追吹。 亂聲吹止句により終わる。 |
舞人は登台して出手を舞います。蛇持が中啓という扇に木でできた蛇を載せて登台し舞台中央に置きます。舞人はこれを見つけて喜悦の状を示すような鹿婁を舞います。 蛇をつかみ舞い終わります。 | |
| 当曲舞 | ・還城楽音取 | ||
| ・当曲 | 古楽。 中曲。左方-早只八拍子。右方-八多良八拍子。 拍子十八。半帖以下加。 二帖。 |
||
| 入時 | ・亂序 | 打物は≪亂序≫。龍笛は≪安摩亂聲≫の退吹。 吹止句により終わる。 |
舞人は入手を舞い退出します。 |
装束 別装束 左方・右方ともに同じ装束を用いる。
| ほう 袍 |
紅地顕紋紗に唐草の地紋。 |
| りょうとう 裲襠 |
貫頭衣。紅地唐織物。淡染の生絹の毛縁。前背面に各々2個の六 |
| はかま 袴 |
紅地唐織物。白綾織の帯。裾の紐を足首でくくる。 |
| あかのおおくち 赤大口 |
紅平絹。 |
| あておび 当帯 |
銅製。牡丹唐草の透彫に金鍍金。周囲に覆輪金具。裏は紅綸子。紅八打紐で締める。 |
| し かい 絲鞋 |
白絹糸。底に羊の柔革。中底に畳表。絹紐で締める。 |
| めん 面 |
木製。中面。朱漆塗。吊顎。動目。目は銀箔おき。眉・鬚・顎に黒毛。 (童舞の時は面を用いず挿頭花[紅梅]をつける) |
| む し 牟子 |
紅地金襴に牡丹・唐草の地紋。裏は紅綸子。3本の組紐で結ぶ。 |
| ばち 桴 |
右手に持つ。木製。赤漆塗。3ヵ所に飾り金具。手許に紅唐打紐。(左手は剣印) |
蛇持 左方 ─ 左方襲装束 (袍は着用しない) 右方 ─ 右方襲装束 (袍は着用しない)
| き へび 木蛇 |
木製。左方 ─ 金漆塗で右巻。右方 ─ 銀漆塗で左巻。 (童舞の時は白紙を巻いた輪を用いる) |
| ちゅうけい 中啓 |
末広扇。左方 ─ 金地に松。右方 ─ 銀地に鶴。 |
