行譜正信偈六首引
正信偈に続き念佛和讃を行譜の節でお勤めするもので、和讃が六首唱えられ回向で終わります。 佛光寺派の正信偈には「真譜・行譜・草譜」の3種がありますが、真譜は本山でしか用いられず、草譜は行譜と同じ節なので実質は行譜1種ということになります。 また、念佛和讃には「行譜・草譜・速譜」の3種がありますが、後者ほど節回しが省略されるだけなのでこちらも実質1種ということになります。 そのような訳で「行譜正信偈六首引」は、佛光寺派において最も中心となる差定で日常勤行をはじめ重要法要においても用いられます。
行譜正信偈 (平調 → 黄鐘調)
リンの2打に続いて調声人が一句目を唱え二句目より全員が続きます。
ロ音(B)より始められるこの節は、四句で一つの旋律をなし多少変奏されながら繰り返されます。
レ-ミ ミ ミ ミ ミ シシー | シシレ-ミ ミ ミ シシラ | ラララララララシ | シシシシシシシー
小休止の後、調声人が「善導獨明・・・」を唱え次の句より全員が続きます。
ホ音(E)より始められる後半の節も、四句で一つの旋律をなします。
8拍/8拍/8拍/11拍と四句目が11拍のため前半より延びやかに聞こえます。
ミ ミ ミ ミ ミ シシー | ミ ミ ミ ミ ミ ミ ミー | ソ-ラララララミ ミー | ミ ミ ミ ミ ミ レ-ミ ミーレシーイ
ロ音(B)より始められるこの節は、四句で一つの旋律をなし多少変奏されながら繰り返されます。
レ-ミ ミ ミ ミ ミ シシー | シシレ-ミ ミ ミ シシラ | ラララララララシ | シシシシシシシー
小休止の後、調声人が「善導獨明・・・」を唱え次の句より全員が続きます。
ホ音(E)より始められる後半の節も、四句で一つの旋律をなします。
8拍/8拍/8拍/11拍と四句目が11拍のため前半より延びやかに聞こえます。
ミ ミ ミ ミ ミ シシー | ミ ミ ミ ミ ミ ミ ミー | ソ-ラララララミ ミー | ミ ミ ミ ミ ミ レ-ミ ミーレシーイ
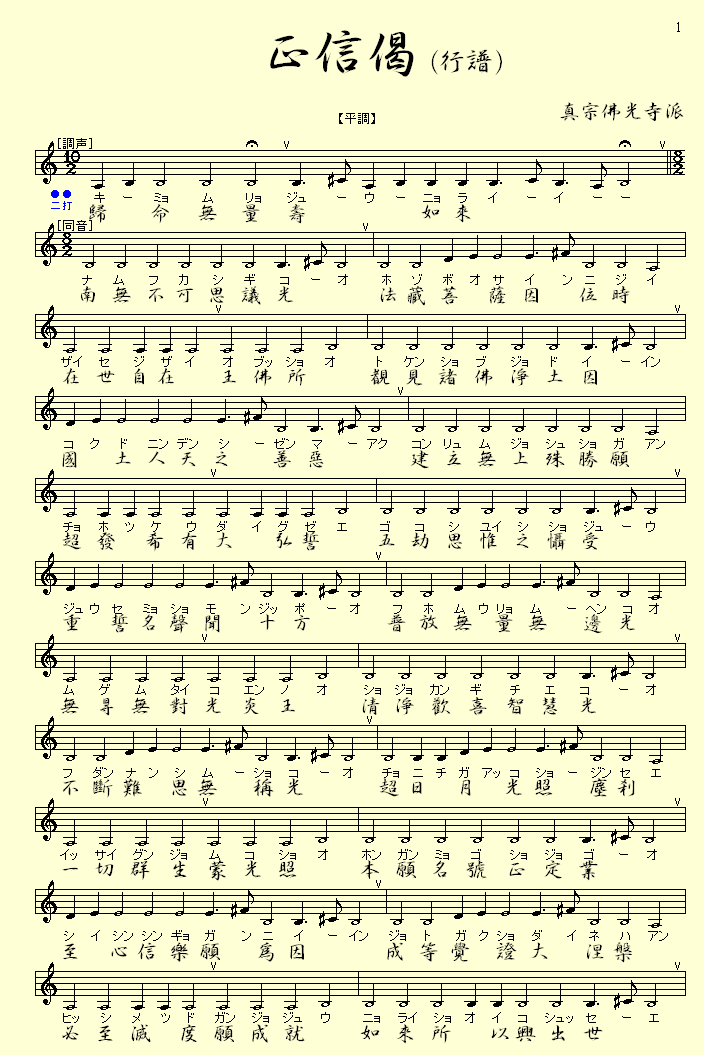
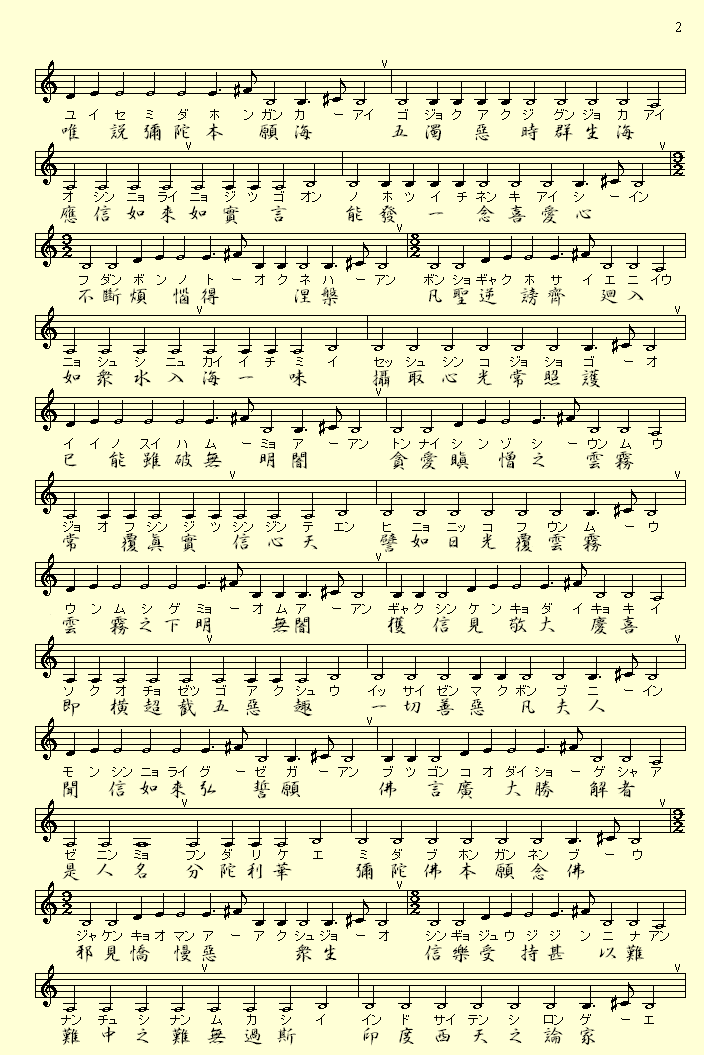
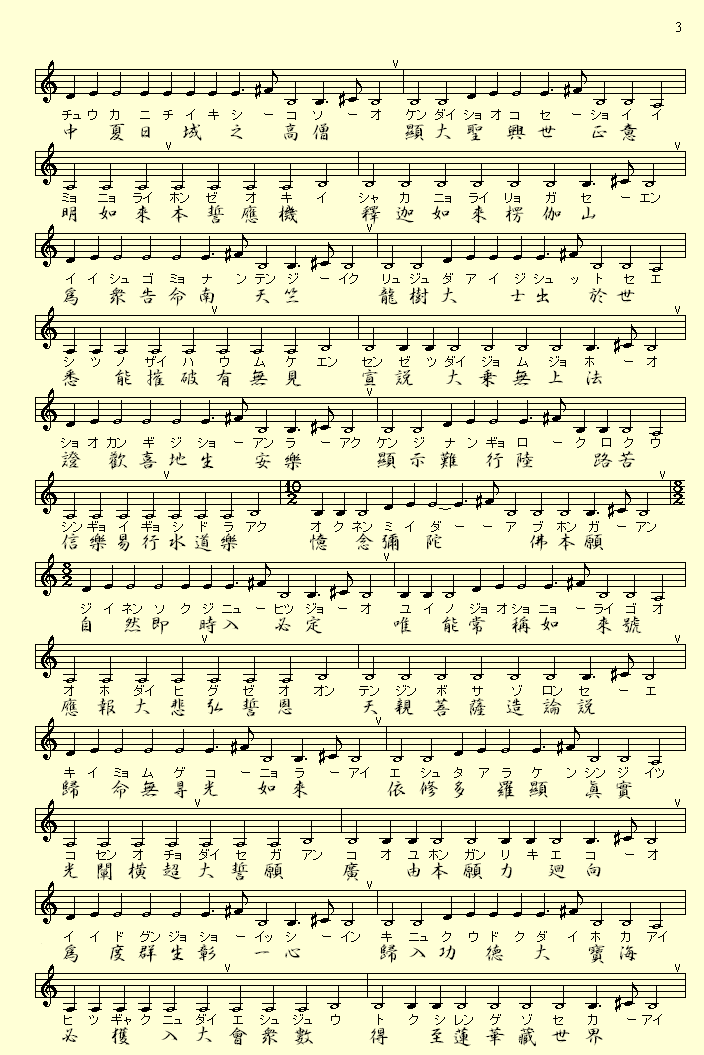
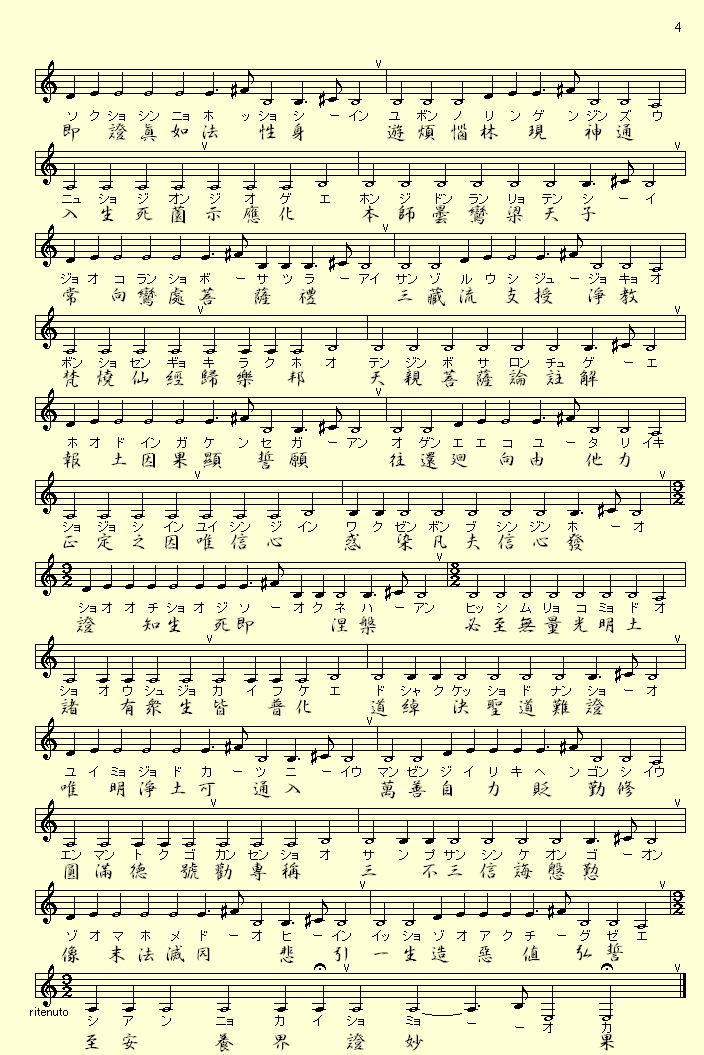
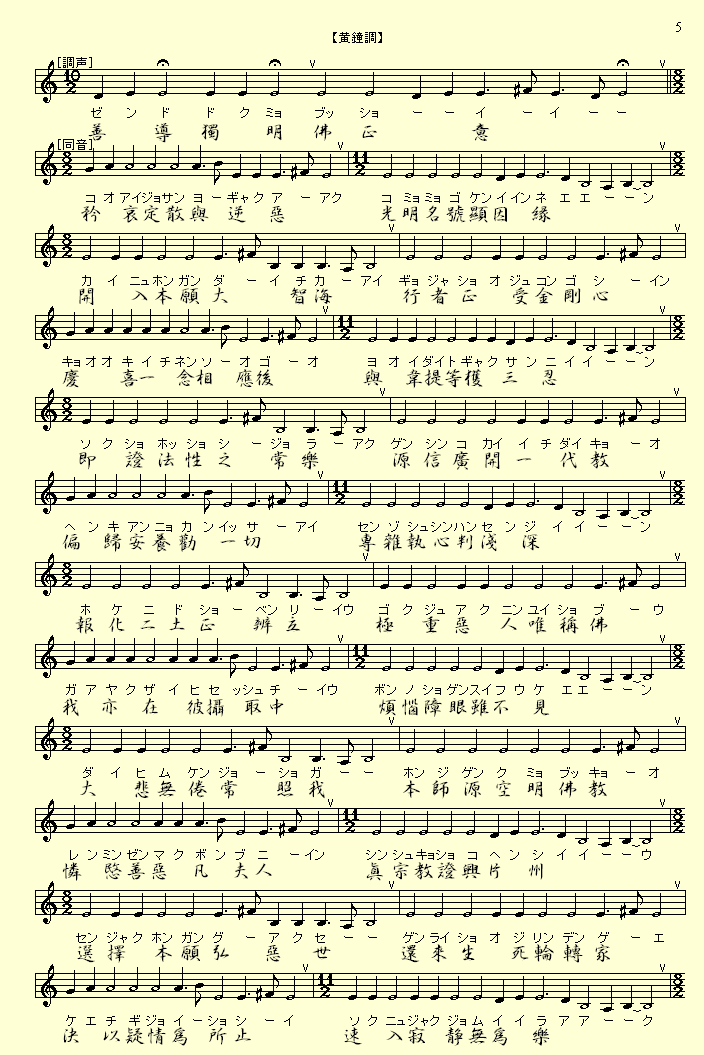
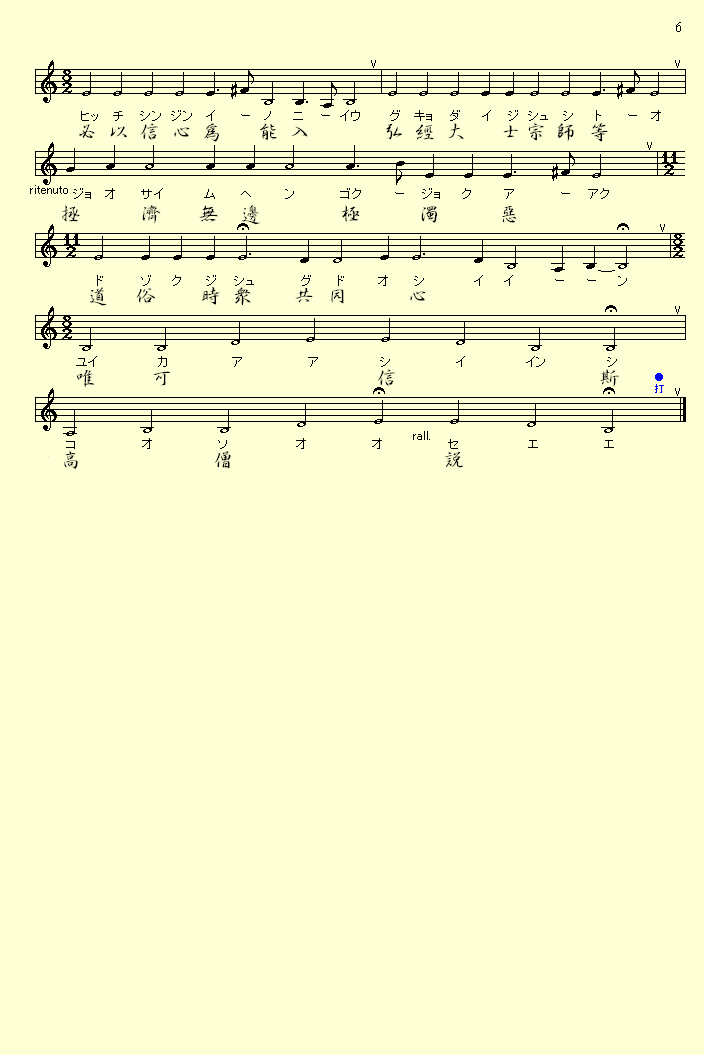
初重念佛和讃 (平調)
念佛和讃は「初重・二重・三重」の3つの節で構成され、
六首引では和讃を二首ずつ交えながら進められます。
ロ音(B)より始められる初重念佛は調声人に続いて計4回念佛が延びやかに唱えられます。
続く和讃は初重念佛の節に基づき作られ、調声人が一句目を唱え二句目より全員が続きます。
初重念佛調声 | 同音 | 一首目調声 | 同音 | 念佛 | 二首目調声 | 同音 | 念佛
六首引では和讃を二首ずつ交えながら進められます。
ロ音(B)より始められる初重念佛は調声人に続いて計4回念佛が延びやかに唱えられます。
続く和讃は初重念佛の節に基づき作られ、調声人が一句目を唱え二句目より全員が続きます。
初重念佛調声 | 同音 | 一首目調声 | 同音 | 念佛 | 二首目調声 | 同音 | 念佛
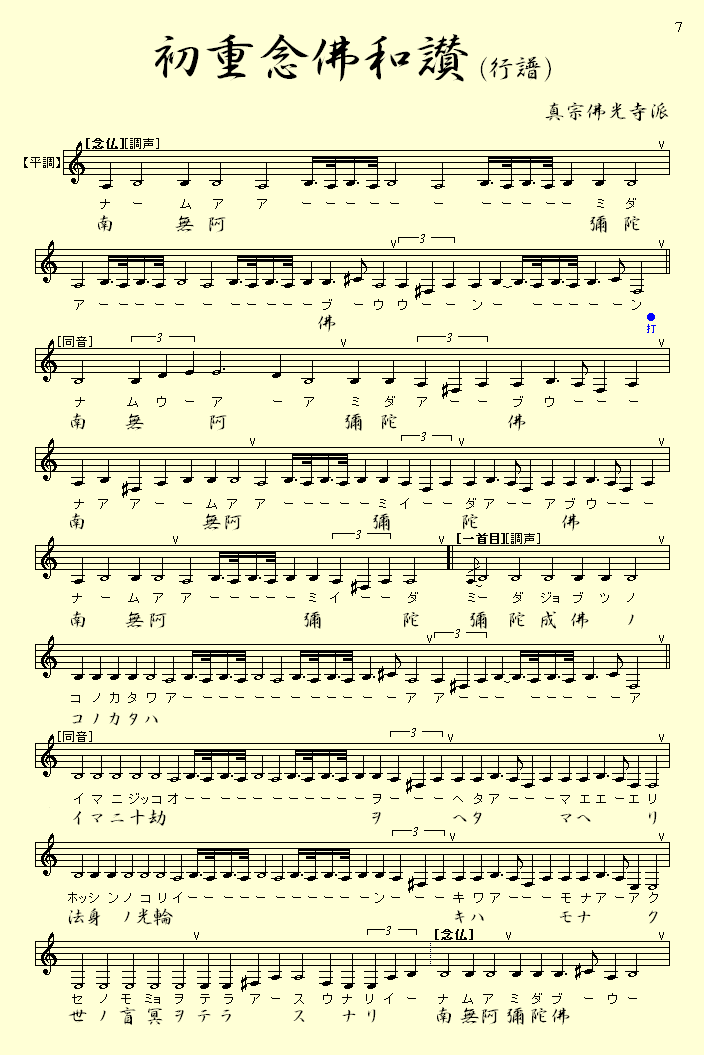
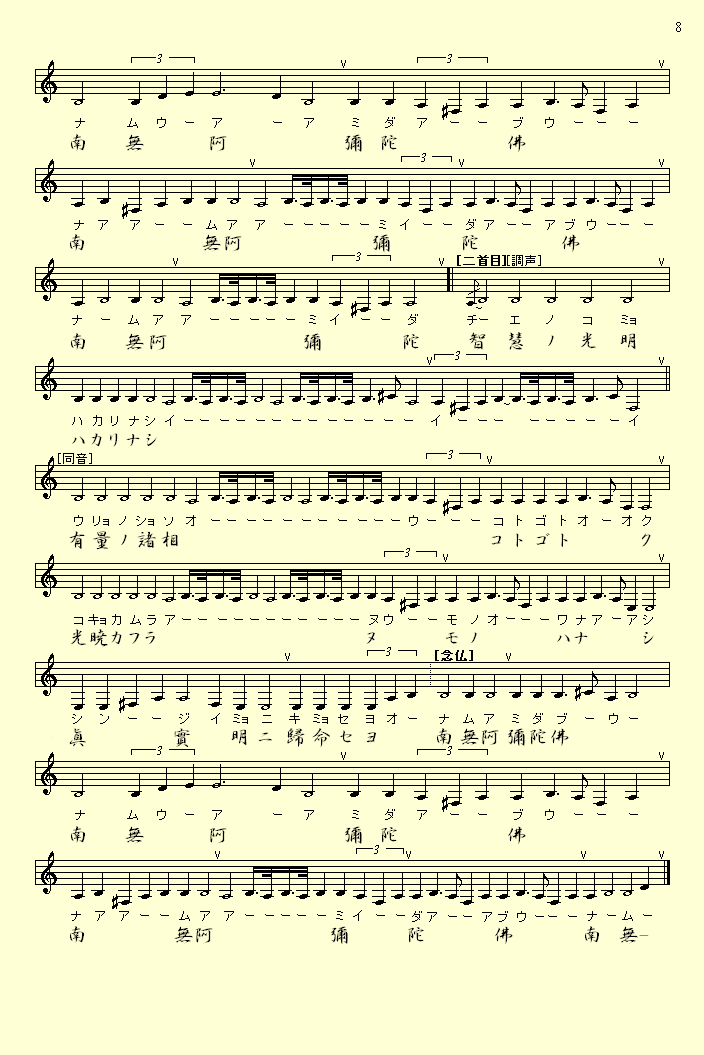
二重念佛和讃 (黄鐘調)
ホ音(E)より始められる二重念佛は調声人に続いて計4回念佛が延びやかに唱えられます。
続く和讃は二重念佛の節に基づき作られ、調声人が一句目を唱え二句目より全員が続きます。
二重念佛調声 | 同音 | 三首目調声 | 同音 | 念佛 | 四首目調声 | 同音 | 念佛
続く和讃は二重念佛の節に基づき作られ、調声人が一句目を唱え二句目より全員が続きます。
二重念佛調声 | 同音 | 三首目調声 | 同音 | 念佛 | 四首目調声 | 同音 | 念佛
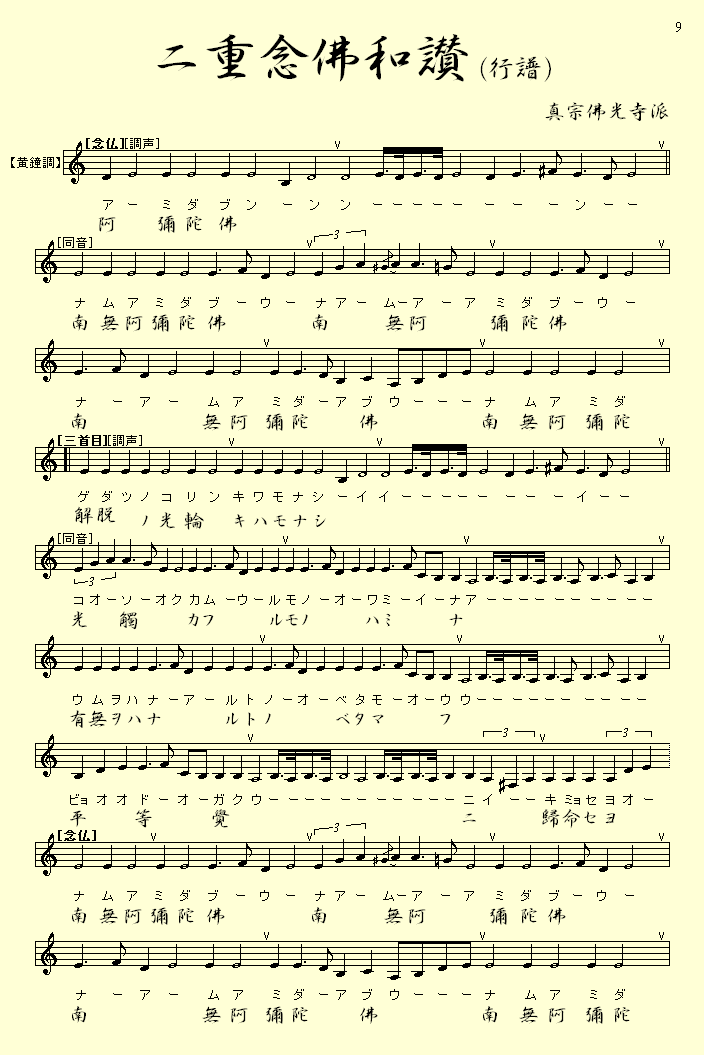
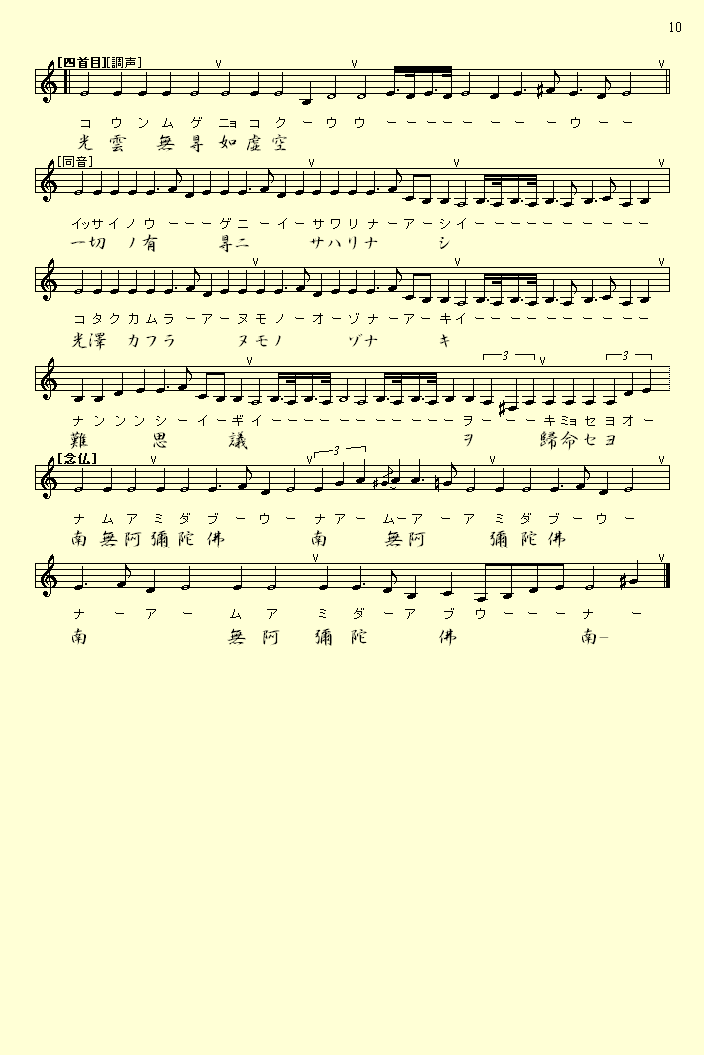
三重念佛和讃 (壱越調)
イ音(A)より始められる三重念佛は調声人に続いて計3回念佛が延びやかに唱えられます。
続く和讃は三重念佛の節に基づき作られ、調声人が一句目を唱え二句目より全員が続きます。
三重念佛調声 | 同音 | 五首目調声 | 同音 | 念佛 | 六首目調声 | 同音
続く和讃は三重念佛の節に基づき作られ、調声人が一句目を唱え二句目より全員が続きます。
三重念佛調声 | 同音 | 五首目調声 | 同音 | 念佛 | 六首目調声 | 同音
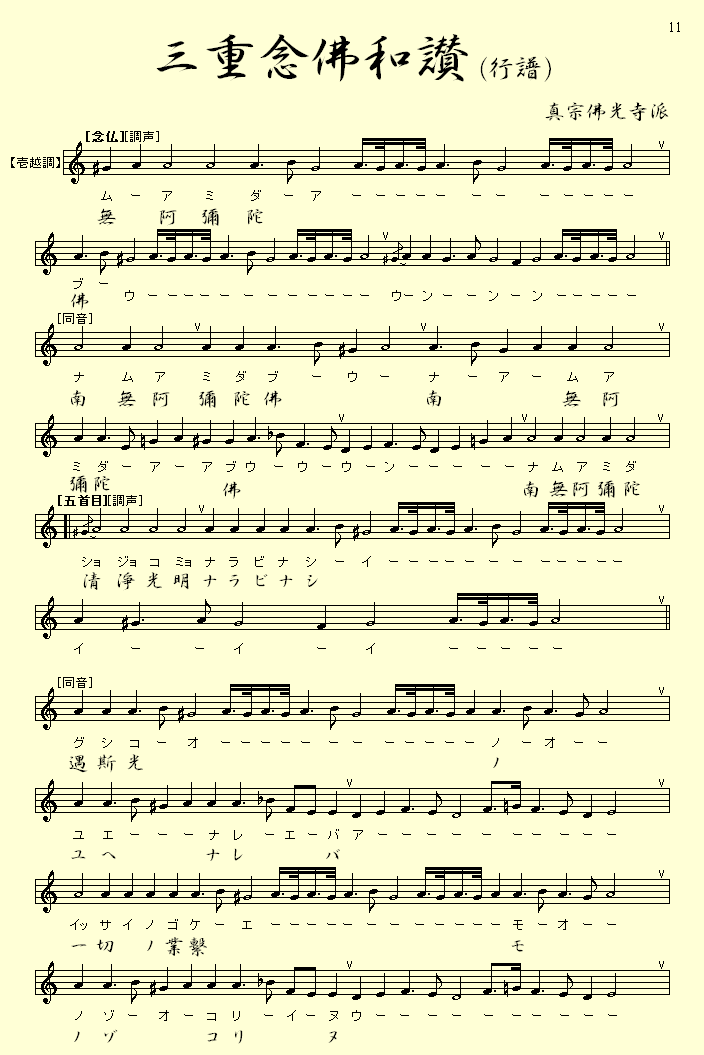
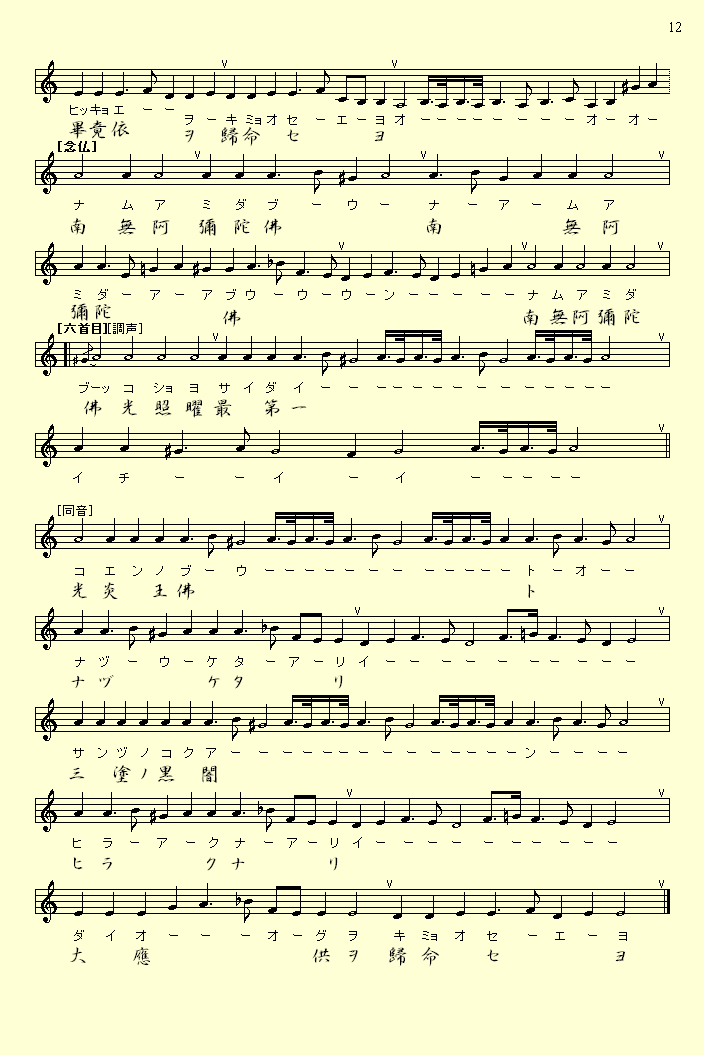
回向 願以 (黄鐘調)
念佛和讃に続き回向が勤められます。
調声人が一句目を唱え二句目より全員が続きリンの3打を伴ないながらこの勤行は終わります。
哀愁をおびた美しい節回しは、短いながらも佛光寺派の御家流を良く表した一曲と言えます。
調声人が一句目を唱え二句目より全員が続きリンの3打を伴ないながらこの勤行は終わります。
哀愁をおびた美しい節回しは、短いながらも佛光寺派の御家流を良く表した一曲と言えます。
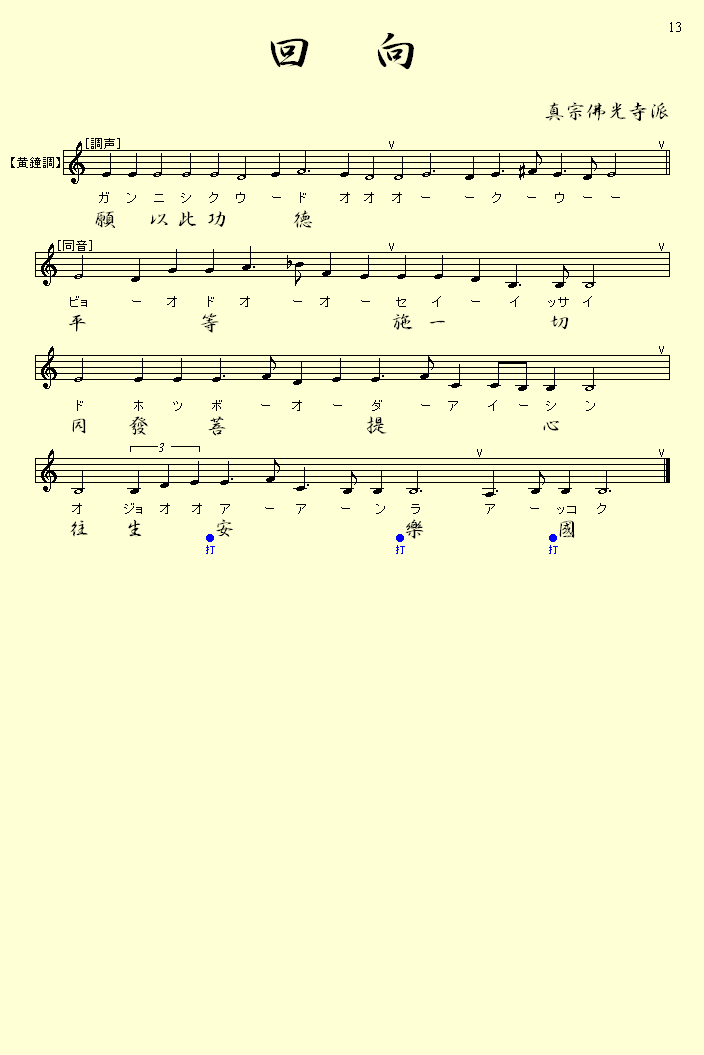
佛光寺第29代 眞照上人著
『真宗佛光寺派 五線声明集』 昭和52年発行
及び
本山下附
『真宗佛光寺派 声明録音集A』
を参照しました
※実際の声調を忠実に採譜している訳ではないことをご了承ください。
2008.4 作成
『真宗佛光寺派 五線声明集』 昭和52年発行
及び
本山下附
『真宗佛光寺派 声明録音集A』
を参照しました
※実際の声調を忠実に採譜している訳ではないことをご了承ください。
2008.4 作成
彌陀成佛の このかたは
いまに十劫を へたまへり
法身の光輪きはもなく
世の盲冥を てらすなり
二首目
智慧の光明はかりなし
有量の諸相ことごとく
光暁かふらぬものはなし
眞實明に歸命せよ
解脱の光輪きはもなし
光觸かふるものはみな
有無をはなると のべたまふ
平等覺に歸命せよ
四首目
光雲無碍如虚空
一切の有碍に さはりなし
光澤かふらぬものぞなき
難思議を歸命せよ
清淨光明ならびなし
遇斯光のゆへなれば
一切の業繋も のぞこりぬ
畢竟依を歸命せよ
六首目
佛光照曜最第一
光炎王佛と なづけたり
三塗の黒闇ひらくなり
大應供を歸命せよ
願以此功徳
平等施一切
同發菩提心
往生安樂國