真宗十派
親鸞聖人の血脈を中心とする『本願寺派(西)』『大谷派(東)』。 門弟たちによる『高田派』『興正派』『佛光寺派』『木辺派』及び『出雲路派』『誠照寺派』『三門徒派』『山元派』をあわせて真宗十派といいます。 聖人は『親鸞は弟子一人ももたずさふらふ〜歎異抄 第六条〜』と師弟関係を否定し、自分にとって共に阿弥陀仏の教えに生きるものは同行同朋であると称し、教団構成には否定的でした。 しかし聖人の教えが広がれば広がるほど諸国に門徒が増えていきます。聖人没後、血脈を中心に始まった本願寺は法系伝持を主張して教団の統括を図ります。 それに対し諸国門徒は自立教団的色彩を強めていきました。このことにより多数の宗派に分かれていくこととなります。
越後配流の後、東国布教により親鸞聖人には多くの門弟ができます。 その中で、栃木県高田の地に始まった高田門徒が勢力を広げ初期真宗教団の主流となります→『高田派』。 のちにこの高田門徒は和田門徒や荒木門徒を分岐させます。 和田門徒の系譜から越前へと広がり→『誠照寺派』『三門徒派』『山元派』、 荒木門徒の系譜をひく了源は京都山科に興正寺を創建し、ここに興正寺・佛光寺系の教団が始まります。 同じ頃、横曽根門徒の系統に属する滋賀県木辺の錦織寺も滋賀県から奈良県にかけて展開しました→『木辺派』。 聖人の没後、末娘らによって東山大谷に廟堂が造られ、やがて「本願寺」の寺号をかかげて独立した教団となります。 しかしこの頃は興正寺・佛光寺系が教勢を広げていました。 その後、蓮如の登場により興正寺・佛光寺系の門主が大半の末寺と共に本願寺に帰依し、佛光寺はその弟が継ぐこととなります→『佛光寺派』。 勢力を増した本願寺は真宗の中核的な存在となり、山科に本願寺を移築しその教線を全国に広げていきます。 江戸時代に入ると本願寺は後継問題によって西本願寺→『本願寺派』と東本願寺→『大谷派』に分裂します。 さらに明治になって興正寺が西本願寺より独立します→『興正派』。
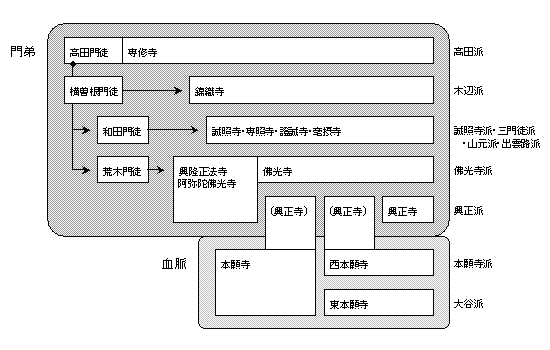
真宗十派の発展